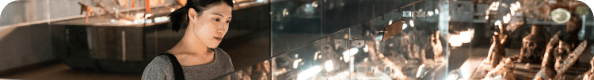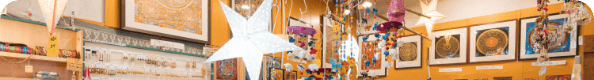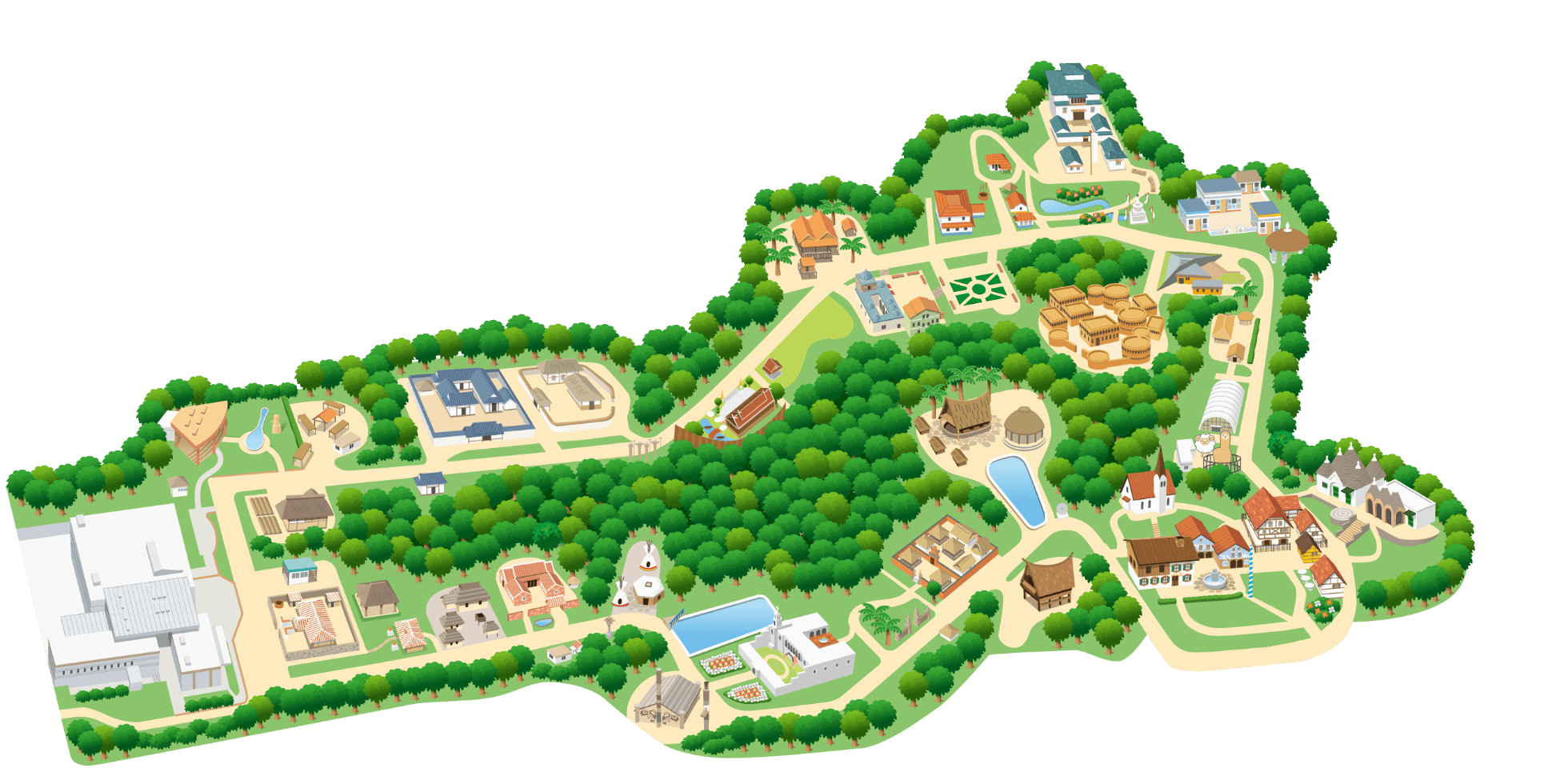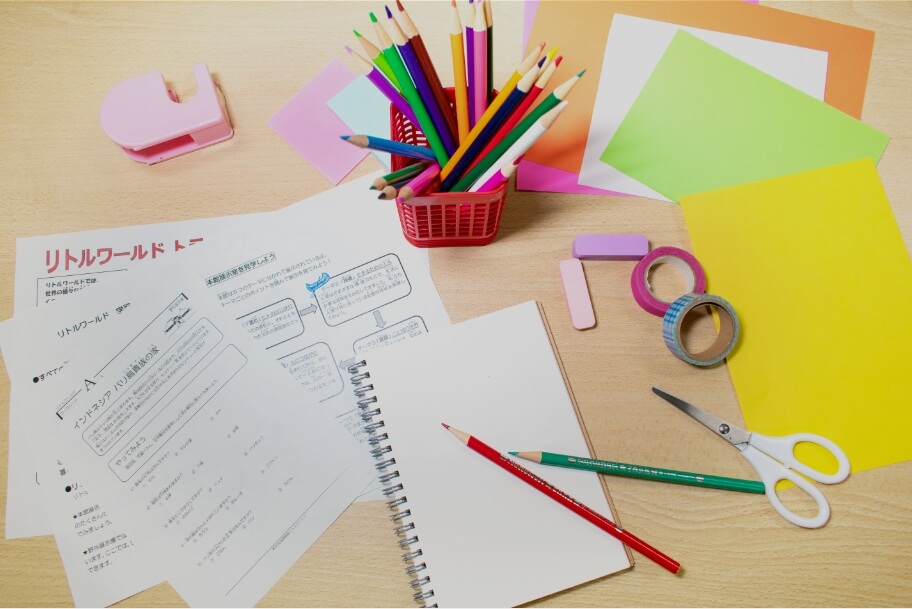exhibition
展示
雪国の伝統家屋
山形県 月山山麓の家
雪国の伝統家屋
山形県 月山山麓の家
豪雪地帯として知られる出羽山地の月山山麓の農家を移築。江戸中期、1767年に建てられた当初は4室だったが、明治中期に増築し、多層型の養蚕農家となった。家屋があった村は、1976年ダム建設にともない廃村になった。
復元年代
1930年代
復元方法
移築復元
現地建築年代
1767年
NEXT

ヒトのはじまりを知る
本館第1室「進化」
雪に耐える、頑強な造り

冬には3~4mの積雪を記録する村の家屋は、中門づくりと呼ばれるL字型の家で、秋田や新潟などの多雪地帯によく見られる伝統家屋です。屋根は茅葺きで、ひと冬に何回も雪下ろしを行います。さらに、家が倒壊しないように、壁の周囲にカヤを張り巡らせるなど、雪深い村では家屋にも暮らしにもさまざまな工夫が必要でした。
ダムに沈んだ村の旧家

日本有数の豪雪地帯に、かつて修験道のメッカとして賑わった出羽山地の月山山麓。ここにダムが建設されるまでは、展示家屋の故郷である小さな村、月山沢がありました。この村のかつての主な生業は水稲耕作と焼畑耕作でしたが、明治になって養蚕が始まり、昭和の初めまでどの家でも大規模に蚕を飼っていました。移築した家は、45戸の月山沢の中でも草分け6人衆と呼ばれる旧家で、300年を超える歴史を誇る家柄でした。
いろりをめぐるしきたり

調理、暖房、団らんの場としてたいせつにされた座敷のいろり。主人は上手のヨコザ、主婦は台所側のカカザ、客は縁側に近いキャクザと席順が決められ、土間側は薪を燃やす場所・キジリとなっていました。また、いろりの枠を踏んではいけない、四足動物を料理しない、爪や髪を燃やさないなど、いろりを巡るしきたりもさまざまにありました。火種は年中絶やさないようにして、新年に新しく火をおこすならわしでした。